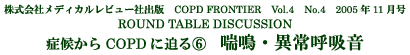
| �o�@�@�@�@�@�@�@�@�ȁ@�@�@�@�@�@�@�@�� | |
| �E�i�� �O���@���W ���s��w��w�@��w�����ȓ��Ȋw�u�� �ċz����Ȋw���� �E�J�ƈ� ��{�@�m ��{���Ȉ�@�i���s�s�j�@�� |
�E�ċz����� ���@�g�L ���s�{����ȑ�w�ċz��a�Ԑ���w������ �E�z����� ���q�@�X�� �k��a�@�z��ȕ����� |
| ���{���F�@2005�N8��10���@�@�@�ꏊ�F�@���s�z�e���I�[�N�� |
|
| �@�m���ɍŋ߁A�f�ÂŒ��f��Ă��ʂ����܂茩�����Ȃ��Ȃ����悤�ȋC������B�������A�ċz���ُ̈�ЂƂƂ��Ă݂Ă��Arhonchus�Awheeze�Astridor�Ȃǂ��܂��܂Ȏ�ނ�����A���ꂼ�ꌴ���ƂȂ鎾�����قȂ邱�Ƃ��킩��B �@����͎�ɒ��f�����i�ċz���ƐS���j�ɏœ_�����ĂāA4��COPD�Ǘ����͂��Ă����������B���ׂĂ��u�b���ċ}�������𗈂����v�Ǘ�Ȃ̂����A���f�����ƏǏ�E�w���ʐ^�ECT�E�S�d�}���Ƃ炵���킹�āA�����̌�����˂��~�߂Ă����ߒ��������[���B�ŐV�̈�Ë@����g�킸�Ƃ��A����Ȃ��Ƃ܂Œ��f�ŗ\�z��������̂��A�Ƌ������ꂽ�B |
|
| ���@�Տ��ɖ𗧂��f�Ƃ� �ċz���ɂ���Ď�����ސ�����  ���@�O���@�@�{���̃e�[�}�́u�b�E�ُ�ċz���v�Ȃ̂ł����A���f�����͐l�ɂ���Ă��܂��܂ȉ��߂�����A�p��ꂵ�Ă����Ȃ��ƍ������܂��B�����ł܂���{�搶�ɁA�T�^�I�Ȍċz���̕��ނɂ��Đ������������A���̌�Ǘ��1���Љ�Ă��������āA�ǂ������_�����Ȃ̂����A���ɒ��f�����𒆐S�ɑ��p�I�Ɍ��Ă��������Ǝv���܂��B�ł͐�{�搶���肢���܂��B ���@�O���@�@�{���̃e�[�}�́u�b�E�ُ�ċz���v�Ȃ̂ł����A���f�����͐l�ɂ���Ă��܂��܂ȉ��߂�����A�p��ꂵ�Ă����Ȃ��ƍ������܂��B�����ł܂���{�搶�ɁA�T�^�I�Ȍċz���̕��ނɂ��Đ������������A���̌�Ǘ��1���Љ�Ă��������āA�ǂ������_�����Ȃ̂����A���ɒ��f�����𒆐S�ɑ��p�I�Ɍ��Ă��������Ǝv���܂��B�ł͐�{�搶���肢���܂��B ���@��{�@�@�܂��A���f�̃|�C���g������1�i�������N���b�N�j�ɂ܂Ƃ߂܂����B����͐����ɂ�������Ă��邱�Ƃł����A����ċz���̎�ނƐ���A���ꂩ�畛�G���ɂ��ẮA���ʂƂ��A�A�������f�����Ƃ��A�傫���A�����A�����Ȃǂɒ��ӂ��܂��B�ŋ߂͂��܂蒮�f����g��Ȃ��J�ƈ�̐搶�������炵���A�������f��Ă܂��ƁA����܂Œ��f�Ȃǂ��Ă���������Ƃ͂Ȃ��ƁA���҂���ɂ悭�����܂��B��͂芳�҂�����A���f��ĂĂ��炤�Ɖ������S������ ���@��{�@�@�܂��A���f�̃|�C���g������1�i�������N���b�N�j�ɂ܂Ƃ߂܂����B����͐����ɂ�������Ă��邱�Ƃł����A����ċz���̎�ނƐ���A���ꂩ�畛�G���ɂ��ẮA���ʂƂ��A�A�������f�����Ƃ��A�傫���A�����A�����Ȃǂɒ��ӂ��܂��B�ŋ߂͂��܂蒮�f����g��Ȃ��J�ƈ�̐搶�������炵���A�������f��Ă܂��ƁA����܂Œ��f�Ȃǂ��Ă���������Ƃ͂Ȃ��ƁA���҂���ɂ悭�����܂��B��͂芳�҂�����A���f��ĂĂ��炤�Ɖ������S�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E��֑����j |
��A�܂��܂����f����g�����f�ÂƂ����̂��Տ��I�ɈӖ�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B �@���͂����ċ��s��w���������������≫�ꌧ�������a�@�ŋ{�鐪�l�Y�搶���璮�f�����ɂ��ďڂ��������Ă��������܂����B�����ɂ͒����ɂ��Ċw�p�I�ɏڂ����L�ڂ���Ă��Ă��A���̐��炢���ɂ��Ď����ɃA�v���[�`����̂��A�Ƃ������L�q�͈ӊO�ɏ��Ȃ��̂ł��B �@�����Տ��ƂɂƂ��Ē����̐���Ǝ����Ƃ̂Ȃ��肪�킩��Ȃ���Β��f���鎖�ɂ��܂�Ӗ�������܂���B���f�����͖�f��Տ����������Ƌ��ɕa�C�̏����f�f�ɏd�v�ȃt�@�N�^�[��1�ł���Ǝv���܂��B ���@�����x�ɐڂ��镔���Œ������ �C�ǁE�C�ǎx���ُ͈� ���@��{�@�@�ċz���̕��ނ�����2�i�������N���b�N�j�ɂ܂Ƃ߂܂����B�܂�����ċz���ł��B����ɂ͋C�lj��A�C�ǁE�C�ǎx���A�x�E����3������܂��B�x�E���͖����x�ɐڂ��镔���Œ��悳��A�ċC�Ɣ�ׂċz�C�ɋ���������܂��B�܂��A�C�lj��ƋC�ǁE�C�ǎx���͔x�̒������ɐڂ��镔���Œ��悳��A�ċC�ɋ���������܂��B �@����1�́A�ُ퉹�i���G���j�ł����A�ċz���̌���E����������1�ł��B���ꂩ��A�����x�ɐڂ��镔���Œ��悳�ꂽ�C�ǁE�C�ǎx���ُ͈퉹�Ƃ݂Ȃ���܂��B���Ȃ킿�A�x�E���͔x�E���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E��֑����j |
�������g�������悳��鉹�ł����A�x�E�����E������ԁA���Ƃ��Δx����x����Ȃǂ�alveolar damage�ł͔g���͔x�E��ʉ߂����ɋC�����璼�ړ`���̂ŁA�C�ǁE�C�ǎx���Ƃ��Ē������̂ł��i�}1�F�����}�E�������N���b�N�j�B �@�ُ퉹�̒��ɂ́A�A�����̃����ƒf�����̃���������܂��B�����āA�A���������̂����Arhonchus�Awheeze�͂ǂ�����A��ɌċC�ɒ��悳��鉹�ŁAwheeze�͋C�ǎx�����k���Ă��鉹�ł��B�ł�����C�ǎx�g����𓊗^����Ə������܂��B���s�b�`�̘A���������ł��Brhonchus�Ƃ����̂͋C�ǎx�ɉ������l�܂������т����Ƃ��������s�b�`�̘A���������ł��B �@�z�C�̎��ɕ��������s�b�`�̘A����������stridor�Ƃ����A�z�C�̎��Ƀu�[�b�Ƃ����������܂����A�q���̏ꍇ�͈ٕ����뚋�����Ƃ��N���[�v�ȂǁA��l�̏ꍇ�͎�ᇂ�A�C�ǎx���j�ȂǑ����C���̋���̂Ƃ��ɒ��悳��܂��B�ł�����wheeze�͓T�^�I�ȋC�ǎx�b���Arhonchus�͋C�ǎx���Ȃǂ̉��ǐ������Astridor�͑����C���̕ǐ������Ƃ����ӂ��ɂƂ炦�Ă��܂��B �@���ꂩ�����1�ُ̈퉹�͒f���������ŁAcoarse crackle��fine crackle�Ɛ����ɂ͋L�ڂ���Ă���̂ł����A���ۂɔ��ʂ���̂͂Ȃ��Ȃ�����Ǝv���܂��Bfine crackle���z�C�̏�������I���܂Œ��悳���̂́A�������Ԏ����x���ۏǂ̏ꍇ�Ƃ����Ă��܂��B���ꂩ��coarse crackle�́A����͐��A���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����֑����j |
| �����Ă���̂ł����A�z�C�̏����ɒ��悳���ꍇ�́A�C�ǎx���ȂNjC���̉��ǂ̏ꍇ�ł��B �@�܂��Aalveolar damage�̂Ƃ���coarse crackle�͋z�C�ƌċC�ɂ܂������Ē��悳���Ǝ��͋�������̂ł����A����͐����ɂ͂Ȃ��Ȃ������ĂȂ��̂ł��B���������̌o������A���̂悤�ȉ������悳���ꍇ�ɂ͔x���A�x����A�S�s�S�A�C�ǎx�g���ǁADPB�Ȃǂ�alveolar damage��z�肵�č����x���Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B �@���̑��́Apleural friction rub�Ȃǂ�����܂��B ���@�O���@�@���肪�Ƃ��������܂����B �@�ł͐�{�搶�A�Ǘ�1�ɂ��ĊȒP�ɏЉ�Ă��������A���ꂩ����ɒ��f�����ɏœ_�ĂāA�ǂ�������肪���邩�����ĉ������B ���@�Ǘ�1 �R�R������ň��艻�������b�E�ċz������}�������𗈂����Ǘ� ���@�Տ��ɖ𗧂��f�Ƃ� �ċz���ɂ���Ď�����ސ����� ���@��{�@�@�Ǘ�1�i�������N���b�N�j��68�̏����ŁA�i������40 pack years�AFletcher-Hugh-Jones�U�x���x�̘J�쐫�ċz����̂���COPD�ł��B�R�R������̋z���ŗ��������Ă����̂ł����A2004�N8�������ɕ��ׂ������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E��֑����j |
��A�J�쎞�̚b�ƌċz����𗈂����A�^��ႂ��P������Ƃ������Ƃ�9��4���ɋ~�}���@���܂����B �@���̎���X���ʐ^�͑S�̂ɉߖc���ŁA�E��cost-phrenic angle���݉����A�ES10�ɂ킸����consolidation��F�߂܂� ���i�}2�F�Ǘ�1��X���ʐ^�E�������N���b�N�j�B�܂����̂Ƃ��ɂ́A37.3���̔��M������A�����̕���ƃ`�A�m�[�[�A�p�ċz������A�z�C���ɕ��ċz�ْ̋���F�߂܂����B �@���f�����́A�z�C�ƌċC�ɂ܂�����coarse crackle�ƁA�C�ǁE�C�ǎx���������ɕ������܂����B�����āA�����������ƍD�����̑�����F�߂܂����BCRP��3.87mg/dL �Ə㏸���A����ÏW������128�{�ł����B���@����CT���B��܂�����A�E�x�ɏ��ʂ̋���������A�ES10�̂Ƃ����consolidation ��F�߂܂����i�}3�FCT�ʐ^�E�������N���b�N�j�B �@�����ŁA���^���x���Ƌ���������COPD�̋}�������ɂ��}���ċz�s�S�Ƃƍl���A�K�`�t���L�T�V���𓊗^�����Ƃ���A7����ɔ������������퉻���A����X����̉A�e���������܂����B���������̑��D�_������475/��L�Ƃ����̂́A�����x�̍D�_���㏸�ƍl���Ă����Ǝv���܂��B�����asth-matic component�ƍl���Ă����̂ł��傤���B ���@�O���@�@���肪�Ƃ��������܂����B �@���f�����ɒ��ڂ��܂��ƁA�����ďo���ɚb�悷��Ƃ������Ƃ�1�ł� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E��֑����j |
�ˁB���ꂩ��E�w���ŋC�ǁE�C�ǎx���Ƌz�ċC�ɂ܂�����coarse crackle�悵���B �@�܂������ċC���ɚb�悷��Ƃ����_�ł����A���̊��҂���́A�J�쎞�̚b�����o���Ă����Ƃ������Ƃł��B���ʂ̌ċz�̎��ɂ͚b�͕������Ȃ�����ǂ��A�\���ďo������ƚb����������B���搶�A���̂ւ����ł����B  ���@����@�@���̊��҂���́A�i������40 pack years�ł����A�x�@�\�̓_�ɂ����Ă��A1�b��37.43%�ŕǐ���Q������A������%1�b�ʂ�50%�����Əd�ǂ�COPD���ƍl�����܂��BCOPD�̊��҂���ɂ����鋭���ċC�ďo���̚b�ł��̂ŁA���Ԃ�ċC���ɋC�������E���āA���̂��߂ɚb���������Ă���̂ł͂Ȃ����Ɛ��@����܂��B ���@�O���@�@COPD�̒��f�����Ƃ��āA���Ìċz���ɂ͕������Ȃ�����ǂ��A�����ďo������A�^��������ƚb����������B�����1�̏����Ƃ��Ă�����x�F�m����Ă���Ǝv���̂ł��B�������������ł����ł��傤���A��{�搶�B ����{�@�@�͂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����֑����j |
| ���@�z�ċC�ɂ܂�����coarse crackle����x����ސ� ���@�O���@�@���̎��̋C�ǁE�C�ǎx���Ƌz�ċC�ɂ܂�����coarse crackle�悵���ƂƂ����A����Ɋւ��Ă͐�{�搶�A�ǂ̂悤�ɉ��߂��Ă�������Ⴂ�܂����B ���@��{�@�@���͂����������������z�C�ƌċC�ɂ܂������Ă���ŏ��ɐ�������alveolar damage��L����x�����ƍl���܂��B����͔x���Ƃ��ĕa�@�ɑ���܂����B���̌㊦��ÏW�����A�}�C�R�v���Y�}�R�̂��㏸�������ߔ��^���x���Ƃ��Ă���ɑΉ�����R�ۖ�𓊗^���A���킹�Ď_�f�Ö@���s���܂����B ���@�O���@�@�Ⴂ����ɂȂ�قǁA��{�搶��������������Ƃ���A���܂蒮�f���Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��Ă��邱�Ƃ͊m���Ȃ̂ł����A���̉E�w���ŁA�������������������蒮�f����Đf�f�E���ÂɌ��ѕt������̂́A��͂���ɑ厖�Ȃ��Ƃ��낤�Ǝv���܂��ˁB �@����X�ʐ^�ŁAcost-phrenic angle�Ɋm���ɔ����e������ACT���B���ď��߂�S10�ɉ�����͂�x���a��������Ƃ������Ƃ��킩��܂����A���̑O�ɂ��łɒ��f�Ŕx���ɂ��G�����Ɛf�f�����Ă���ꂽ�A��������Ă���ꂽ�Ƃ������Ƃł��ˁB ���@��{�@�@�͂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E��֑����j |
���@�O���@�@�킩��܂����B��������ƁA�C�ǁE�C�ǎx�������������E�w���������ɕ������邱�Ǝ��́A��͂���Ɉُ킾�Ƃ������Ƃł�낵���ł����B ����{�@�@�͂��B����Ŕx���̐g�̏����ɍ��v���Ă��邽�ߔx���Ɛf�f���܂����B ���@�O���@�@�킩��܂����B���q�搶�A�S�d�}�i�}4�F�������N���b�N�j�����Ă��������܂����B  ���@���q�@�@�ُ�Ȃ��Ə����Ă��������Ă���Ƃ���ŁA���퓴�����ŁA��������ł��BCOPD�̂��ɂ́A�U�A�V aVF��P�g�������Ȃ��B�܂�E�S���ׂ̏������Ȃ��Ƃ������Ƃł��ˁB�x��P�Ƃ����������Ȃ��BP�g����2.5mm�ȏオ��ł��B���ꂩ��E�S���ׂƂ����̂́A�E���Έʂł�������A����V1�ł�R�g�̑����ł�������A�ꍇ�ɂ���Ă͉E�r�u���b�N�̏o���ł������肷��Ǝv���܂����A���������E�S�n�ɂ����鏊���͔F�߂��Ȃ��̂ŁA����ȐS�d�}�Ƃ������Ƃł悢�Ǝv���܂��B ���@�O���@�@��{�搶�Ə�������v���܂����̂ŁA�ꉞ�S�d�}�͐��킾�Ƃ������Ƃł��ˁB �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E��֑����j |
�@���ꂩ��S���̒��f������āA��{�搶�̕��ŐS���������ƋL�ڂ���Ă���܂����A�u���ŃM�����b�v���Ȃ��v�ƁA����͂ǂ̂悤�ɉ��߂���悢�̂ł��傤���B ���@���q�@�@�M�����b�v�Ƃ����̂́A���̊��҂���͖�������96�ƁA�����̂ł����A�ߏ�S���̇V���Ƃ��W���Ƃ����̂��������܂��ƁA�^���^���A�^���^���A�^���^���ƁA�n�������Ă���悤�ȉ��ɂȂ�킯�ł��B �@�V���Ƃ����̂͐S�����g������Ƃ��̉��ŁA�W���Ƃ����̂͐S�[�����k����Ƃ��̉��A�ǂ���������Ȃ�E���̊g���������オ��Ƃ��A�S�[�����オ��ƋN������̂Ȃ̂ŁA�������̎w�W�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B�ł�����M�����b�v���Ȃ���A�������������͂Ȃ��Ƃ������ƂŁA�S�s�S�̏����͂Ȃ��Ƃ����܂��B ���@�O���@�@��������ƁA�S�d�}�����Ɛ�����������Ƃ������Ƃł��ˁB ���@���q�@�@�����ł��ˁB ���@�O���@�@����A�ǎ҂̐搶���ɂ��Ђ��肢�������̂ł����A�x�̒��f�ƁA���ꂩ��S���̒��f�ƁA������͂�ꏊ�����ɒ����Ă������������Ǝv���܂��B���q�搶�ɂ́A�ǗႲ�ƂɐS���ɂ��Ẳ��߂����肢�������Ǝv���܂��B �@���̏Ǘ�͂���ł�낵����ł��傤���B�S���͐��ŃM�����b�v�Ȃ��A�ċz�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����֑����j |
| �́A�����ċC���ɚb�悷�邱�Ƃ���d�ǂ�COPD�A�܂��E�w���ŋC�ǁE�C�ǎx���ƁA�z�ċC�ɂ܂�����coarse crackle�悳�ꂽ���Ƃ���x����f�f����܂����B���ɑ厖�Ȓ��f�������Ǝv���܂��B ���@�Ǘ�2 �S�s�S���������A�}�������𗈂����Ǘ� ���@���f������crackle�ƏǏ� �S�s�S�ɂ��x����l������ ���@�O���@�@���́A�S�s�S���������ċ}�������𗈂����Ǘ�2�i�������N���b�N�j�ł��B��{�搶�A��낵�����肢���܂��B ���@��{�@�@���̊��҂���́A���Ƃ��ƐS�s�S�������āA���Î��̌ċz���������Ƃ������ƂŁA���@����f����܂����B�ł�����A�S�s�S��COPD���������āA�ċz��Q�����������Ƃ����Ǘ�ł��B �@smoker��80 pack years�ł��B���Ƃ��Ɠ��A�a�Ƃ����S�ǂ̎��Â��Ă���A�y�[�X���[�J�[�������Ă��܂��B �@2003�N11��������F-H-J���އV�x�̘J�쐫�ċz�����i���Ă���A��ԉ��ɂȂ�����ΖA��̑��tႂ��o���悤�ɂȂ�������2004�N12��8���ɗ��@���Ă��܂��B �@���f�f�f�ł́A�ċz���͌��サ�Ă���A�J���y���b�悵�܂��B���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E��֑����j |
����z�ċC�ɂ܂��������f�����́A�����炭��coarse crackle��F�߂܂��B�S���̍ŋ��_�͂�����ƐS�|���̕��ɂ���̂ł͂Ȃ����ȂƎv���܂����B�܂��A�M�����b�v��F�߂܂����B�o�`��w�͂��肻���ł����B �@���f�̏����Ƃ��ďǗ�1�Ɠ����悤��alveolar damage�̏���������A�z�C�Ɍy��wheeze������܂����B �@X�����������ł͔x�͂��ߖc���ŁA�����]���p�͂��݉����Ă��܂��B�t�Ԃ̔���Ɣx�啔�̊g���͔x�̂��������^�킹�܂��B�܂��S�A�e�����g�債�Ă��܂��i�}5�F�Ǘ�2��X���ʐ^�E�������N���b�N�j�B �@�x�@�\�ɂ��ẮA���ʁA���ċz����債�Ă��āAshort trachea������ꍇ�́A1�b�ʂ�1L�ȉ��Ƃ����̂����ʂȂ̂ł����A1�b�ʂ�1.76L�Ƃ��Ȃ�悢�ł��BCOPD�����S�s�S����̂̂Ƃ��͂��������ɂȂ�̂ł��傤���B �@���ꂩ��12�U���ŐS�����̊��O���k�ƐS�[�ד�������AST-T�ُ̈킪�F�߂��܂����B���ꂩ�疖���������́A�����������������Ă���܂�����ǂ��A�D�_���̑����͂���܂���B���Â͕\���Ɏ����Ă���Ƃ���ł��B�����ł́A�S�@�\�E�S�d�}�̕]�������Ă��������āA�S�s�S��COPD�̑����Ɋ֘A���Ă���̂��f�������Ǝv���܂��B ���@�O���@�@��������ɖʔ����ǗႾ�Ǝv���܂��B�܂��x�@�\�����ɂ��Ċ��搶�ɉ�����Ă������������̂ł� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E��֑����j |
���B ���@����@�@1�b�ʂ�1.76L�A�T���u�^���[���z�����1.84L�ŁA���P����4.5%�ł��̂ʼnt���͂Ȃ��ƍl�����܂��B �@���ꂩ��1�b���́A64.0%�ŁA�ǐ���Q�͂���Ɣ��f�ł��܂����A%1�b�ʂ��݂܂���63.1%�ŁACOPD�Ƃ��Ă͒������Ƃ������ƂɂȂ邩�Ǝv���܂��BV25�AV50�́A�����C���̕ǂf���܂����A�����ǐ���Q�ł���1L/s��邱�Ƃ������̂ɁAV50��1L/s���Ă��܂��B�ł�����ǐ���Q�͂��邪�A���x�͂���Ȃɋ����Ȃ��Ƃ܂Ƃ߂���Ǝv���܂��B ���@�O���@�@��������ƁA���搶�̕��͂ɂ��A�x�@�\�̐��l�͂�����Ђǂ�COPD�ł͂Ȃ��Ƃ������ƂŁA���̊��҂���̌ċz����̏Ǐ�́A���Ȃ��Ƃ�������COPD�����ł͐��������ɂ����A����ł�낵���ł��ˁB ���@����@�@�͂��B ���@�O���@�@�ł͒��q�搶�A���f�����E�S�J�e�[�e���E�S�d�}�ɂ��ĉ�������肢���܂��B ���@���q�@�@���f�̏����ɂ��ẮA�搶���ɉ����y�Ȃ��Ǝv���̂ł����A���B��coarse crackle�����Ƃ��A���邢�͔w���̓��ɉ��̕��Œ����Ƃ����� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����֑����j |
| ���ɂ́A�x�E�ɐ����l�܂������Ƃ����Ӗ��ŁA�x�������̂Ƃ��ɋN���鏊���Ƃ������Ƃ��l���܂��B���ɐ��X���ʐ^�����Ă��܂��܂����̂ŁA���̂悤�Ȃ������������Ԃł���A���傤�ǔx���Ɠ����悤�Ȕx�E�����o�t�A�R�o�t�Ŗ��܂����悤�ȉ�������Ƃ������Ƃ͂���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B ���@��{�@�@���̏ꍇ�͋z�C�ƌċC�ɂ܂�����̂ł��傤���B����Ƃ��z�C�݂̂ł����B���̂ւm�肽���ł����E�E�E�E�E�E ���@�O���@�@���搶�A�������ł����B ���@����@�@����͎��̈�ۂ����킩��܂��A�z�C�ɂ�苭���ł��B�ċC�ɂ������܂�����̂ł��傤����ǂ��A�z�C����ċC������ł�������Ă����悤�Ȉ�ۂ������Ă��܂��B ���@��{�@�@�z�C�ƌċC�ɂ܂�����̂��Aalveolar damage�����������Ƃ��ĈӋ`�����邩�ƍl���Ă����̂ł����B�z�C������������A�ނ���x���ۏǂ��^�����낤�Ǝv���܂��B���̂ւ�ɂ��ċ����Ă���������Ǝv���܂��B ���@�O���@�@�搶������������Ă���Ƃ���Acoarse crackle��fine crackle�͔��ɓ���Ǝv���܂��B�����ɂ���Ă��A�S�s�S�������coarse crackle���o�܂��Ƃ�����܂����Afine crackle���S�s�S�̏����Ƃ��ċL�ڂ���Ă���ꍇ������܂��̂ŁA��͂�coarse��fine �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E��֑����j |
�Ƃ����͔̂��ɓ���Ƃ��낪����Ǝv���܂��B �@�Ǘ�2�̏ꍇ�́A����crackle�ƁA�Ǐ�Ƃ̊֘A���݂Ă݂܂��傤�B�A��̔S�tႂ�\�o����Ƃ̂��Ƃł����A�x������N�����ƖA���ႂ��o�Ă���Ƃ悭�����܂��B�Տ��I�ɂ͂ǂ��ł����A���搶�B ���@����@�@�����ł��ˁA���̏Ǘ�ł͖A��̔S�tႂƂ��A�ċz����̂��߂ɉ��ɂȂ�Ȃ������Ƃ��A���������Ǐ���S�s�S�ɂ��x����l������Ǝv���܂��B ���@�}�������̌����� �x�R�����S���R���� ���@�O���@�@���q�搶�A�����ĐS�J�e�[�e���ƐS�d�}�����̉�������肢���܂��B ���@���q�@�@�S���J�e�[�e�������ɂ��A�������̑���ɂ킽�苷��a�ς��F�߂��܂����A�o�C�p�X�p��PTCA�ɂ�茌�s�Č���������Ă��܂��̂ŁA�S�؋������N���肤��̈�Ƃ��ẮA�o�C�p�X�̕ǂ��Ă��鍶����������}�����ƉE����������}�������l�����܂��B�S�d�}��A�S�؍[�ǂɂȂ��Ă��镔�ʂ�����܂��̂ŁA�S�@�\���ቺ���Ă���A�S�s�S�ɂȂ�₷����Ԃƍl�����܂��B ���@��{�@�@���̊��҂���̐S�؍[�ǂ̏ꏊ�Ƃ����̂́A��ɂǂ��ɂ���̂ł��傤���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E��֑����j |
���@���q�@�@�}6�A�S�d�}�i�}6�F�������N���b�N�j�ł̓��Y���͐S�[�U����VVI�y�[�X���[�J�[�ɂ��y�[�V���O����x�����Ă��܂��BI��aVL�̂Ƃ낱�ňُ�Q�g��F�߂܂��̂ŁA���ǂ̍[�ǂł��B���ꂩ��S�[�ד�������̂ŁA�S�[�̓������Ȃ��Ȃ������A��w�S�@�\�͒ቺ���Ă���Ǝv���܂��B �@�����������Ƃ��l����A�S�����̂̃|���v�@�\���ቺ���Ă���Ǘ�ł��낤�B�S�s�S���N�����x�[�X�ƂȂ�S���̕a�C���A�͂����葶�݂��Ă���Ƃ������Ƃ��A�S�d�}����͂킩��܂��B ���@�O���@�@�E�S���ׂ͂͂��̂ł��傤���B ���@���q�@�@�S�[�ד��ɂȂ��Ă��܂��Ă���̂ŁA�S�[�̂��Ƃ͂킩����Ȃ��̂ł����A���ɉE���Έʂ�����܂��AV1��R������قǍ����Ȃ��̂ŁA�E�S���ׂ����������͂Ȃ��Ǝv���܂��B ���@�O���@�@�������܂��ƁACOPD�������ŐS���Ɉُ�𗈂����Ƃ������́A��͂�S�������Ƃ��Ƃ̌����ł���Ƃ������Ƃł��ˁB�x����̉e���͂��܂�o�Ă��Ȃ��̂ł��ˁB ���@���q�@�@�͂��A�x���S�Ƃ����悤�ȏ����͐S�d�}��͂Ȃ��Ǝv���܂��B ���@�O���@�@1���f���������̂ł����A�S���b���Ƃ����̂́A��͂肱��Ȃ��̂Ȃ̂ł����B�����ċz��Ȉ�́A�S���b���Ƃ������Ƃ��悭�g���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����֑����j |
| �ł����A���ꂪ������S���b���Ȃ̂ł��傤���B ���@���q�@�@�S���b���ł����Ǝv���܂��B ���@�O���@�@�S���b���̒�`�Ƃ������̂́E�E ���@���q�@�@���f������A���ʂ̐S�s�S�̂Ƃ��ɂ́Acoarse crackle���������āA�x�E�����܂��Ă����̂ł��傤���A�C�ǎx�S���Ȃǂɂ��������ƁA�C�ǎx�̂��k���U������Awheeze���o�Ă���킯�ł��ˁB��������ƁA�b���Ɠ����悤�ȉ�����������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���������_�ŐS���b���Ƃ����܂��B �@�����A�S���b���́A���f�ł��b���Ƃ͈���āAcoarse crackle����������Ƃ����Ƃ���ŁA������x�����킩��܂��B���ꂩ��A��{�搶�������Ă����������悤�ȃM�����b�v�Ƃ����A������������������������悤�Ȃ��Ƃ���A���f�����ł��ӕʂł���ꍇ�́A�\������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B ���@�O���@�@����͂��������Ӗ��Ŕ��ɋM�d�ȏǗ�ł��ˁB���̏ꍇ�ł��A��{�搶�͂���𗠕t������悤�Ȓ��f��������������Ƃ��Ă���������Ǝv���܂��B���̏Ǘ�Ɋւ��ẮACOPD������܂����A���Ȃ��Ƃ��}�������̌����ƂȂ����̂́A�S�s�S�����ƂŁA��������S�s�S�ł��ˁB �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E��֑����j |
���@���q�@�@�͂��A�������S�����ɂ�鍶�S�s�S�ł��B ���@�Ǘ�3 �b������ɂ��}���ċz�s�S�ƂȂ��������Ì������Ɉڍs���� �b�����q��L����Ǘ� ���@�x�@�\��COPD�A���f�����͚b���l ���@�O���@�@�ł��Ǘ�3�i�������N���b�N�j�̚b�����q��L����COPD�̏Ǘ���A��{�搶���肢���܂��B ���@��{�@�@73�̏����ŁA�i������33����73�܂�1��20�{�ŁA80 pack years�ł��B10�N���炢�O����J�쐫�ċz�������܂����B�b�ƌċz������������Ƃ������Ƃł��B1�������炢�O�ɕ��ׂ���������A���������Ƒ��ꂵ���āA�b�����߁A�߂��̕a�@����f���Ă��̂܂܋C�ǎx�b���Ƃ��ē��@���Ă��܂����B�����Ŏ_�f�Ö@�A�A�~�m�t�B���������Ò��A�t���^�C�h�z���ƁA�b���Ƃ��Ď��Â��ꂽ�̂ł����A�ǂ����Ă��悭�Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂŁA���@���ɕa�@���o���ė��@����܂����B���̂Ƃ��ɂ͕p�ċz�Ōċz�����ɋꂵ���A�`�A�m�[�[�A��ʂ�l���̂ނ��݂�����܂����B�M��̋��s�ŁA���ċz����債�āA���ċz���g���Ȃ���ċz���Ă��܂����BJugular�؍���1���w�Ɣ��ɒZ�k���Ă��܂����B �@�_�f�O�a�x��92%�Œʏ�̉�b���o���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E��֑����j |
����B�ċz�퉹������ŁA�b���z�C�ƌċC�ɂ܂������Ē��悳��܂����B���x�̌ċz�s�S���b������ƍl���܂����B�S���͐��ŃM�����b�v�͂���܂���B�S�땔�͓��������A�قƂ�lj������炢�ɂ���܂����B�����͐G�m���܂���ł����B �@���ɏd�v����̂��߁A���̂Ƃ��ċz�@�\�̌����͂ł��܂���ł����B�x�͉ߖc���ʼn��u���͕��ቻ���Ă��܂��i�}7�F�Ǘ�3��X���ʐ^�E�������N���b�N�j�B �@���������̔���������7,900/��L�A�D�_��8%�A���D�_��632/��L�A����ٓIIgE��850IU/mL�ACRP�͉A���ł��B�D�_���������x�㏸���Ă��܂����B �@�_�f�z���������`���v���h�j�]������Ö������^���܂����B���̌�A�v���h�j�]������1��20mg7���Ԍo�����^���A���̂��ƃt���`�J�]���ƃ`�I�g���s�E�����z�����܂����B1������ɂ͌ċz��Ԃ���������悭�Ȃ��āA���͑S�����C�ɓ��퐶���𑗂��Ă��܂��B �@������ɂȂ��Čċz�@�\�����������Ƃ���A1�b�ʂ�1.18L�A1�b����55.93%�A�t����6.8%�ŁA�t���Ȃ��Ɣ��f���܂��āA�ŋ߂ł̓`�I�g���s�E�����z�������āA�ċz��Ԃ͈��肵�Ă��܂��B �@���̂悤�ȏǗ�͚b���Ƃ����̂��A����Ƃ��b�����q�ł���COPD�Ƃ����̂ł��傤���B�ǂ��������������A���f��������������b�����q�̂���COPD�Ƃ����̂������Ă���������Ǝv���܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����֑����j |
| ���@�O���@�@�ł́A�܂����搶�A������ɓ����Ă���̔x�@�\�̉�������肢���܂��B ���@����@�@�_�f�O�a�x��96%�ŁA��ቺ���Ă��܂��BFVC��2.11L����܂��̂ŁA�N����l����ƁA���̒��x���ȂƎv���܂��B1�b�ʂ�1.18L�ŁA1�b����55.92%�ł��̂ŁA�ǐ���Q�͂���Ƃ����܂��B%1�b�ʂ�73.75%�ł��̂Œ����ǂ�COPD���Ǝv���܂��BV50�AV25�͂��Ȃ藎���Ă��܂��̂ŁA�����C���̏�Q�͂���ƍl�����܂����A1�b�ʂ̉t����6.8%�ł��̂ʼnt���͂Ȃ��ƍl�����܂��B ���@�O���@�@���肪�Ƃ��������܂��B�}8�A�S�d�}�i�}8�F�������N���b�N�j�ɂ��ẮA���q�搶�������ł��傤���B ���@���q�@�@�S�d�}�͓��Ɉُ�͔F�߂��܂���B�E�S���ׂ̏��������ɂ���܂��A�S�؏�Q�̏������Ȃ��Ƃ������ł悢�Ǝv���܂��B ���@�O���@�@��{�搶�A���a���̒��ɁA���@���ɕp�ċz�Ŋ�ʁE�l���������Ə�����Ă���̂ł����B ���@��{�@�@�}���ċz�s�S�̊��҂����@�����ꍇ�A�����Δ����ƁA�ނ��݂Ƃ������̂�����܂��B�����炭�E�S���ׂ��A���̂Ƃ��ꎞ�I�ɋN�����������킩��܂���B ���@�O���@�@��������ƁA���̕���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E��֑����j |
��Ƃ��ɐS�d�}���B���Ă���A�E�S���ׂ̏����́E�E�E�E ���@��{�@�@��������������Ȃ��ł��ˁB���̂Ƃ��͂����S�d�}���B��]�T���Ȃ��āB ���@�O���@�@��������ƒ��q�搶�A����������ʁE�l�������̏ꍇ�́A�ǂ������S�d�}���\������܂����B ���@���q�@�@�b������̂Ƃ��Ƃ������Ƃł��ˁB�ꍇ�ɂ���ẮA������͂��Ȃ�̓����p���ɂȂ�Ǝv���܂����A�E�S���ׂ̏������o�Ă���\���͂���Ǝv���܂��B ���@�O���@�@���ƁA���̕��̒��f�����͂������ł����B ���@��{�@�@���̂Ƃ��A���f�����́A�b����͂�z�C�ƌċC�ɂ܂������Ă������̂ł����A���Ƃ͌ċz�������ゾ�Ƃ����ȊO�ɂ͓��ɉ�������܂���B ���@�O���@�@��������ƚb������̂Ƃ��ɓT�^�I�Ȓ��f�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB �@���A�w��ł��A�b�����q�̂���COPD���ǂ��l�����炢���̂��Ƃ����A�b����COPD�͍�������̂��Ƃ��������܂߂āA���ɂ��낢��z�b�g�ȃf�B�X�J�b�V����������Ƃ���ł��B���搶�A���̏Ǘ�Ɋւ��ẮA���̂ւ�ǂ��l������悢�̂ł��傤���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E��֑����j |
���@����@�@�x�@�\�̖ʂ����COPD�ƍl���Ă����Ǝv���̂ł��B�b�����q�ɂ��Ăł����A���̕���33����73�܂�1��20�{���������^�o�R���z���Ă��܂��āA���ɚb���̈��q���������ł��ƁA�^�o�R���z���Ƃ�͂蔭��͋N����܂��B�ł����獡�������b���̂悤�Ȕ�����N�����ꂽ�̂́A�i�������琄�@����A�����COPD�̋}�������ƍl���Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B ���@�O���@�@���A���ɑ厖�Ȃ��Ƃ�������������̂ł����A�����̐l���ACOPD�͍D������̂̉��ǂ��ƔF�����Ă���킯�ł��B������Ɍ���Ίm���ɂ����Ȃ̂ł����A�}�������̎��ɂ́A�D�_�����̉��ǂ��N���Ă��������������Ȃ����A����͂����m������Ă���Ƃ���Ȃ̂ŁA���̏Ǘ�̏ꍇ���A���ׂ�������āA���ꂪ�������ŋ}�������������N�����A���̂Ƃ��ɍD�_�����̉��ǂ��N�����Ěb���l�̔��삪�o���Ƃ����l�����͂������ł��傤���B �@�������͐�{�搶�ɂ��f���������̂ł����A��{�搶�͚b���̕��ł����ɗL���Ȑ搶�ŁA���҂������������f�Ă����܂��̂ŁACOPD�ƚb���̈ٓ��Ɋւ��āA�����Ō��\�ł��̂ŁA���b�����Ă��������܂����B ���@��{�@�@���̏Ǘ�ł́A�������̍D�_�������㏸���Ă��邱�Ƃ�A�b�悷�邱�Ƃ���A�������搶��������������悤��COPD�̚b�����q�܂��͚b���l����Ƃ����ӂ��ɍl���܂����B �@����ł͚b����COPD���ǂ̂悤�ɋ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����֑����j |
| �ʂ���̂��A�Ƃ����ΓK�ȃA�C�f�A�͕����т܂���B���͋i�����A�Ǐ�A������̔x�@�\�Ƃ��̉t���A�C���ߕq�ǁA�\ႂ̉��ǍזE�̎�ށA�������D�_�����Ȃǂ̏����𑍍����Ěb���Ȃ̂��ACOPD�Ȃ̂��A���邢��COPD�̚b�����q�Ȃ̂��f���A�����Â̑I���ɖ��ɗ��ĂĂ��܂��B ���@�Ǘ�4 �C�������}�����������Ǘ� ���@�}�ɋN�������b���f�f�̃|�C���g�� ���@�O���@�@���肪�Ƃ��������܂����B�ł͍Ō�ɐ�{�搶����ACOPD�ɋC�����������ċ}���������A�b�悵������������Љ�������܂��B ���@��{�@�@�Ǘ�4�i�������N���b�N�j�͕\�̒ʂ�ł����A�}�������ŗ��@���ꂽ�Ƃ��́A���a���Ɛg�̏�������C���ɊԈႢ���Ȃ��Ɣ��f�A�����ɓ��@���Ă��炢�܂����B����͓��@��̕a�@�ŎB�e�����C����X���ʐ^�ł��i�}9�F�Ǘ�4��X���ʐ^�E�������N���b�N�j�B �@���̏Ǘ��COPD�ɂ͊ԈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B�C����COPD�̋}�������̌����ƂȂ����Ǘ�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E��֑����j |
���@�O���@�@���ʁA�C���Ƃ����̂͌ċz�������サ�Ă��܂��̂ł����A����COPD�̏ꍇ�́A���Ƃ��ƌċz�������サ�Ă���̂ŁA�ċz�������サ�Ă��邩��Ƃ����ĉ��Ƃ��������A���f��Ȃ��Ȃ�����̂ł��B�܂�X���ʐ^�𐳖ʂ���B���Ă��Ă��A�ꕔ���ɋC��������ꍇ�́ACT���B��Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��ꍇ������A�C���͔��ɐf�f������ł��B �@���̏Ǘ�Ŕ��ɖʔ����ȂƎv�����̂́A�b���o�Ă����Ƃ������Ƃł��ˁB ���@��{�@�@�����ł��B�b�ł����A�}�ɋN�������Ƃ������ƁA�܂��������ɂ�����A�_�f�O�a�x���ቺ�����̂ŁA�C���ɊԈႢ�Ȃ��Ɣ��f���A�~�}���@���Ă��������܂����B ���@�O���@�@�������������o��������̂ł����ACOPD�ŋC�����N����O�͚b�͑S�R�������Ă��Ȃ��āA�C�����N���Ă���}�ɒ��悷��悤�ɂȂ�܂��B����͔��ɉߌċz�����܂��̂ŁA������ċz����̂��߂ɉߌċz�̂Ƃ��ɋN����COPD�̚b��������Ȃ����A���邢�́A�S�s�S���N���Ă��邽�߂ɁA�b���N����̂�������Ȃ��B������ɂ���A�����S�R�b�̂Ȃ��l���A�b�𗈂����o������A�����1�̐ԐM���ł���ˁB �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E��֑����j |
���@��{�@�@�������Ǝv���܂��B ���@�O���@�@���������Ӗ��ł́A����͔��ɑ厖�ȏǗႾ�Ǝv���܂��B���搶�A�������ł����B ���@����@�@���̂Ƃ��肾�Ǝv���܂��B�����ƈ�����ɂ��銳�҂��A�ˑR�b�𗈂��Ƃ����悤�ȏꍇ�ɂ́A�����N���Ă���̂��Ǝv���܂��B ���@���f�Ɋւ���A�h�o�C�X �S���E�ċz���Ƃ��ɒ��J�� ���@�O���@�@����ł́A�Ō�Ɉꌾ���A���f�ɂ��Ẵ����|�C���g�A�h�o�C�X�����肢���܂��B ���@���q�@�@�ċz����𗈂��Ă�������̒��f�ŁA�x��̒��f�ɂ��ẮA�������͐\���グ�邱�Ƃ͂Ȃ��Ǝv���̂ł����A�S���ɂ��ẮA�M�����b�v��A�S�G���A�ٖ��ǂ���������悤�ȏ���������ꍇ�ɂ́A�S�s�S�Ƃ����\���͂��Ȃ荂���Ȃ��Ă��܂��̂ŁA�S�����Ă��������̂͑�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B ���@�O���@�@��{�搶�A�������ł����B ���@��{�@�@�������Ë@�킪���B���A �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����֑����j |
| CT��G�R�[�Ȃǂ������Ă��A��͂蒮�f�͏����f�ÂɌ������Ȃ����̂ł���A�Ƃ������Ƃ�\���グ�����Ǝv���܂��B ���@�O���@�@���搶�A�������ł����B ���@����@�@�x��̒��f�Ƃ����Ă��A�x��Ƃ����͍̂L���ł�����A���|�A���邢�͔w���A����������܂߂āA�\���S�̂ɂ킽���čL�������̂��d�v�ł��B���ꂪ�f�@�����Ō����Ƃ��Ȃ��|�C���g�ŁA���J�ɂ���̂��厖���Ǝv���܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�E��֑����j |
���@�O���@�@���肪�Ƃ��������܂����B �@�����͐�{�搶�ɁA�M�d�ȏǗ��4��Q���������A���f�ɂ��Ă��낢��Ƌ����Ă��������܂����B�����钮�f�Ƃ����̂́A��͂蒮�f��Ă����Ă����������ƂŁA��͂芳�҂���Ƃ̂Ȃ��肪�ł����V�̑����ł͂Ȃ����Ɖ��߂Ċ����܂����B �@�ꏊ�����g�̏������Ƃ邱�Ǝ��̂��a�C���������茩�߂�����ł��̂ŁA���������Ӗ��ŁA���ɎႢ�搶�ɁA���f�Ƃ������̂����Ђ�����x�������āA��ɂ��Ă������������Ǝv���܂��B �@�{���͂ǂ������肪�Ƃ��������܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�I�����܂����j |
�@�{�L���ɂ��ẮA��w�}���o�ŎЁu������Ѓ��f�B�J�����r���[�Ёv�l�̂������̂��ƂɌf�ڂ��Ă���܂��B �@�L�����̎ʐ^����щ�����Ȃǂ��ׂĂ̂��̂ɒ��쌠������܂��B���Ȃ������A�]�p�A�̔��Ȃǂ̓��p���邱�Ƃ��ւ��܂��B |